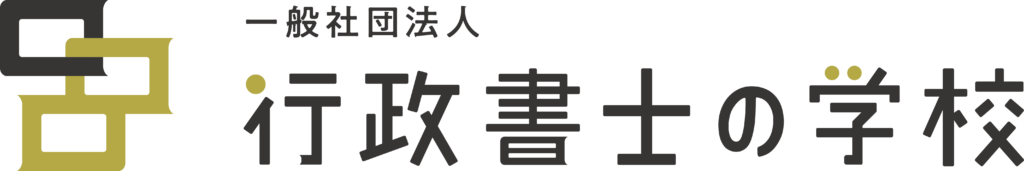行政書士の王道業務といえばなんでしょう?
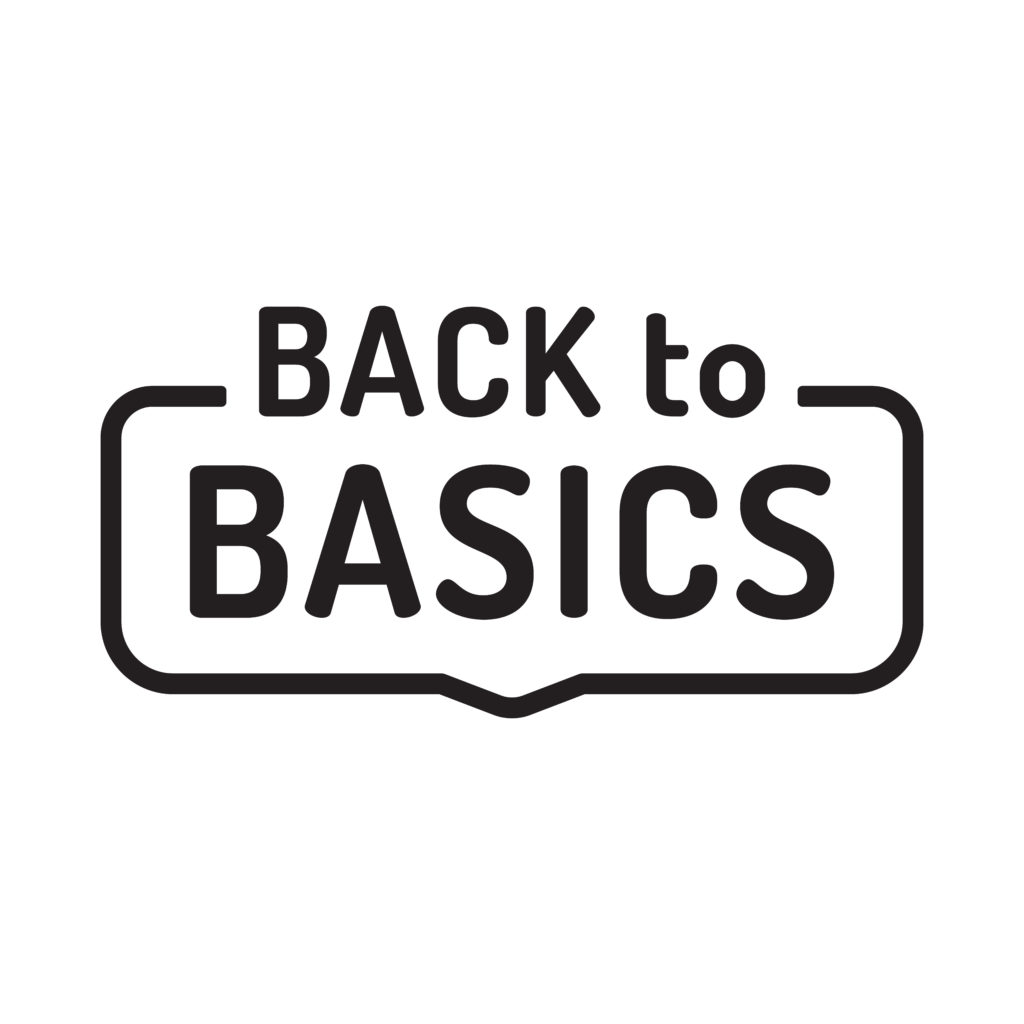
統計をとったことはないですが多くの行政書士が扱っている業務といえば建設業をあげることができます。
なぜなら許可件数を見てみても建設業は圧倒的に多く、産廃業が20万件であるのに比べて40万件以上の許可業者がいますので、それだけ市場が大きい業務といえます。
では下記、そんな王道である建設業を扱うべき理由を見ていきます。
建設業を扱えたほうがいい理由とは
王道業務であるがゆえに、後発で建設業をやっていけないのではないか、既に先輩方が市場を握っているのではないかという声も聞きます。
しかし、行政書士も平均年齢が60歳を超えていると言われていますし、後発でもやり方によっては十分できるほどの市場規模があります。
それにマーケティング的に見ても建設業を扱えたほうがいいのです。
毎年の仕事がある
たとえば産廃関連の許認可は基本的に5年ごとの更新以外は変更事項がなければ業務は発生しません。
一方で建設業はこうした更新許可や変更届以外にも毎年決算変更届という手続きが発生する他、入札や経営審査事項など継続的な業務が発生する可能性があります。
こうした継続的な業務が発生するということは積み上がれば売上が計算できるということ。スポット業務が多く売上が安定しにくい行政書士にとってはとても魅力があるでしょう。
関連業務が多い
建設業を取得している会社は電気工事業の登録、解体工事業の登録、建築士事務所の手続きなどが関係してくることが多いほか、産業廃棄物収集運搬業や産業廃棄物中間処分業などとも相性が非常にいいです。
同じお客様から発生する業務が多いということはその会社からの売上が大きくなるということ。
いわゆるアップセル、クロスセルができるという点でも建設業は魅力です。
王道だからこそ基礎が大事
市場が大きいからこそ、自分の知識次第ではコンサル的なサポートも可能になり、顧問契約に繋げられやすくもなりますが、だからこそ、しっかり基礎を身につけることが大事です。
基礎がなくて応用なんて無理だからです。
手引きや関連書籍もありますが、実際の申請では手引きにあるようなきれいな案件ばかりではないですし、現場で必要になる知識というのはなかなか学ぶ機会がありません。
行政書士の学校の建設業セミナーは全2回に分け、講義の後に申請書を作る宿題を出し、その見直しをするからこそ実践的です。
頭で理解するだけでなく、実践するからこそ頭にはいる。
そして講師と知り合いになることでちょっとしたことで相談できるようにもなるわけです。
ぜひ今後建設業をしっかり身につけていきたいという方はこちらをご覧ください。